軽トレーラーはミニボートの運搬や、水上バイク、農機の運搬など様々な場面で活躍できる車両ですが、軽トレーラーの車検費用が高いと感じることがありますよね。
一般的な整備工場やディーラーに車検に出すと、高額な車検費用が掛かることが多くなっていますが、実は軽トレーラーは点検箇所も少なく、ユーザー車検の方が断然お得なのです。
実際に、私は軽トレーラーをユーザー車検に4回(2024年現在)持ち込んでいますが、すべて一発合格しており、車検費用を抑えることができています。
そこで今回は、車検費用を安く抑えられる軽トレーラーのユーザー車検について、実際の経験をもとに詳しく解説していきます。
- 軽トレーラーの維持費
- 車検費用
- ユーザー車検費用
- ユーザー車検内容と手順
そもそも軽トレーラーとは?

ユーザー車検を受ける前に、軽トレーラーの構造や定義について、しっかりと理解しておく必要があります。
軽トレーラーの定義は、全長が3.4メートル以内、車幅が1.48メートル以内、高さ2メートル以内、最大積載量が350キログラム以下のトレーラーのことで、黄色ナンバーの取得が必須となります。
軽トレーラーの車両重量は150キログラム程度なので、仮に最大積載量である350キログラムを積み込んだとしても、普通免許で運転可能です。【750キログラム以上はけん引免許が必要】
車検の期間については、新車でも2年に一度、受ける必要があります。
軽トレーラーには制動装置であるブレーキが付いておらず、構造的にはリヤカーと同じで、簡単な構造となっているため、個人での点検整備のみでユーザー車検に通すことも可能です。
- 普通免許で運転可能
- 黄色ナンバーが必要
- 車検は2年に一回
軽トレーラーの車検費用と年間維持費は?
| 項目 | ディーラー車検 | ユーザー車検 |
|---|---|---|
| 軽自動車税(年間) | 3,600円 | 3,600円 |
| 車検基本費用(2年) | 約30,000〜40,000円 | 約13,210円 |
| 自賠責保険料(2年) | 車検費用に含む | 5,210円 |
| 自動車重量税(2年) | 車検費用に含む | 6,600円 |
| 検査手数料(2年) | 車検費用に含む | 1,400円 |
| 2年間の合計費用 | 約43,600円前後 | 約13,210円 |
| 年間換算費用 | 約23,600円 | 約6,605円 |
| 年間維持費の差額 | — | 約15,000円安い |
軽トレーラーの車検費用や年間維持費がどれほどかかるのかを、ディーラー車検とユーザー車検を比較してご紹介します。
ディーラーなどで車検を受けた場合
まず、軽自動車税が3600円、整備工場やディーラーで車検を受けた場合には少なくても3~4万円前後。
軽自動車税3600円+車検費用3~4万円前後=43600円前後となり、上記を年間維持費に直すと23600円前後の費用がかかることになります。
ユーザー車検の場合
ユーザー車検にかかる費用は自賠責保険料=5210円、自動車重量税=6600円、・検査手数料 =1400円となっており、合計で13210円かかります。
ディーラーで車検を受けた場合の費用との差額は、3万円前後となり年間維持費に直してみると1万5千円程度違うことになります。
軽トレーラーのユーザー車検の手順と内容について

ここでは、軽トレーラーのユーザー車検を受ける方の為に、車検までの流れについて解説します。
検査予約
軽トレーラーの車検は軽自動車協会で行うため、検査日や時間の予約が必要になります。
予約はネットで簡単に行えますが、メールアドレスなどの登録が必要になりパスワードの設定が必要になりますが、登録をしておかないと予約を取ることはできません。
登録が完了すると予約が可能になり、予約申し込み後に登録したメールアドレスに予約完了の報告と、予約番号が送られてきます。
軽自動車協会にて車検受付
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 自賠責保険料(2年) | 5,210 |
| 自動車重量税(2年) | 6,600 |
| 検査手数料(2年) | 1,400 |
| 合計 | 13,210 |
予約時間にユーザー車検窓口にて車検受付を行いますが、ユーザー車検に慣れていないことを窓口で伝えると、車検を受けるまでの流れが記載されている書類をもらえるので、慣れていない方はここでもらっておくと、後の手続きがスムーズに行えます。
協会内では重量税や、自賠責保険料、検査手数料を支払う窓口が違うため、受付でもらったユーザー車検の手引きに沿って手続きを進めていきましょう。
車検受付時にかかる費用の内訳は
- 自賠責保険料=5210円
- 自動車重量税=6600円
- 検査手数料 =1400円
となっています。
車検開始
車検にかかる費用を支払い終わったら、いよいよ車検ですが軽トレーラーは検査場に入場することなく検査が行われることが一般的で、駐車場に止めた軽トレーラーの側に検査員が来て検査を行います。
検査項目、内容については後述しますが、本当に簡単な検査で10分足らずで検査は完了します。
ちなみに、受付では必要ありませんが、検査員が牽引車両の車検証を確認するので、牽引車両の車検証が必要になります。
検査終了後車検証交付
車検で異常がなければ、検査員に捺印してもらった検査証明書を渡されるので、受付に提出して車検証が交付されます。
車検証が交付されたら承認シールも渡されるので、ナンバーに貼り付けてユーザー車検は完了です。
軽トレーラーのユーザー車検の点検項目と内容について
ここでは、軽トレーラーのユーザー車検予定者が事前に行っておくべき整備や点検項目について解説します。
実際の車検でもチェックされる個所、内容なのでしっかりと確認しておきましょう。
タイヤの溝やひび割れ

まず最初に確認されるのがタイヤの溝です。
車検に通すために必要な溝の深さは1.6㎜が限界なので、これ以下の状態で車検を受けても受かりません。
タイヤは車検場での交換がが難しいので、事前にしっかりと確認して1.6㎜以下であればタイヤ交換をしてから車検を受けましょう。
交換の目安である1.6㎜が分かりにくいという時には、上記画像のスリップサインが出ているかどうかで判断してみましょう。
タイヤのトレッド面(タイヤ表面)とスリップサインが同じ高さであれば、1.6㎜以下になっているので交換が必要になります。
そして、見落としがちなのがタイヤのひび割れです。
毎日乗る車両ではないので仕方がないといえば仕方がないのですが、駐車している時間が長いトレーラーなどはタイヤの位置が変わらず、負担が同じところにかかり続けるためひび割れしやすくなります。
こちらには明確な基準があるわけではありませんが、タイヤにひび割れがあると車検には通らない可能性があるのでチェックしておきましょう。
※下記画像のようなひび割れがあると車検に通らない可能性があるので注意が必要

灯火類

軽トレーラーの車検項目のほとんどが灯火類の確認です。
ブレーキランプ、バックランプ、スモール、左右のウィンカー、ハザードがチェックされるので事前に異常がないか確認し、異常があれば取り替えておきましょう。
各箇所のボルトの緩み、割れの確認

次にチェックされるのが、タイヤを固定しているナットの緩みを点検ハンマーでたたいて確認する作業です。
タイヤのみならず車両のボルトは全て叩いてチェックするので、しっかりと確認しておく必要があります。
駐車装置の確認

軽トレーラーを切り離して駐車装置の確認が行われますが、ブレーキのない軽トレーラーには、タイヤの側にチェーンなどが駐車装置として備え付けてあります。
それをかけて車両が動かないかチェックされるので事前に不具合がないか、しっかりと駐車できるかを事前に確認しておきましょう。
反射板

何でもないような反射板ですが、これが原因となり車検に通らないことが多いので注意が必要です。
軽トレーラーには後方左右に一つずつ、一辺が15㎝以上の正三角形の反射板の取り付けが義務付けられています。
これは軽トレーラーに限らず大型のトレーラーも同じで、少しでも基準に満たないと車検には通りません。
使用中に反射板が割れたり欠けたりしても分かりにくいために、見落としてしまいがちですが、しっかりと確認しておく必要があります(ヒビは問題ない)。
上記画像の反射板の上部にひび割れがありましたが車検には通りました。
しかし、割れて欠けていたりすると車検に通らないので、欠けているのであれば事前に購入して交換しておきましょう。
※反射板は中央穴と左右穴とあるので、ご自身のトレーラーに取り付けられる方を選ぶ必要があります。
個人的な整備で間違いなく車検に通る!
普通自動車や軽自動車もユーザー車検は、ある程度の知識がないと検査場でトラブルが発生した場合の対応が難しく、素人では難しい面があります。
しかし、制動装置の付いていない軽トレーラーは、非常に簡単な構造で点検箇所も少ないため、自分で点検整備しておけば確実に通ります。
簡単にユーザー車検通るのであれば、自分で持って持っていく方が断然お得で、コストの削減につながります。
事前にしっかりと点検整備を行いユーザー車検に臨みましょう。
まとめ
ここまで軽トレーラーのユーザー車検について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
軽トレーラーの車検はユーザー車検が絶対にお得なので、是非ともトライして浮いた費用を必要なアイテムなどの購入費用に回しましょう!
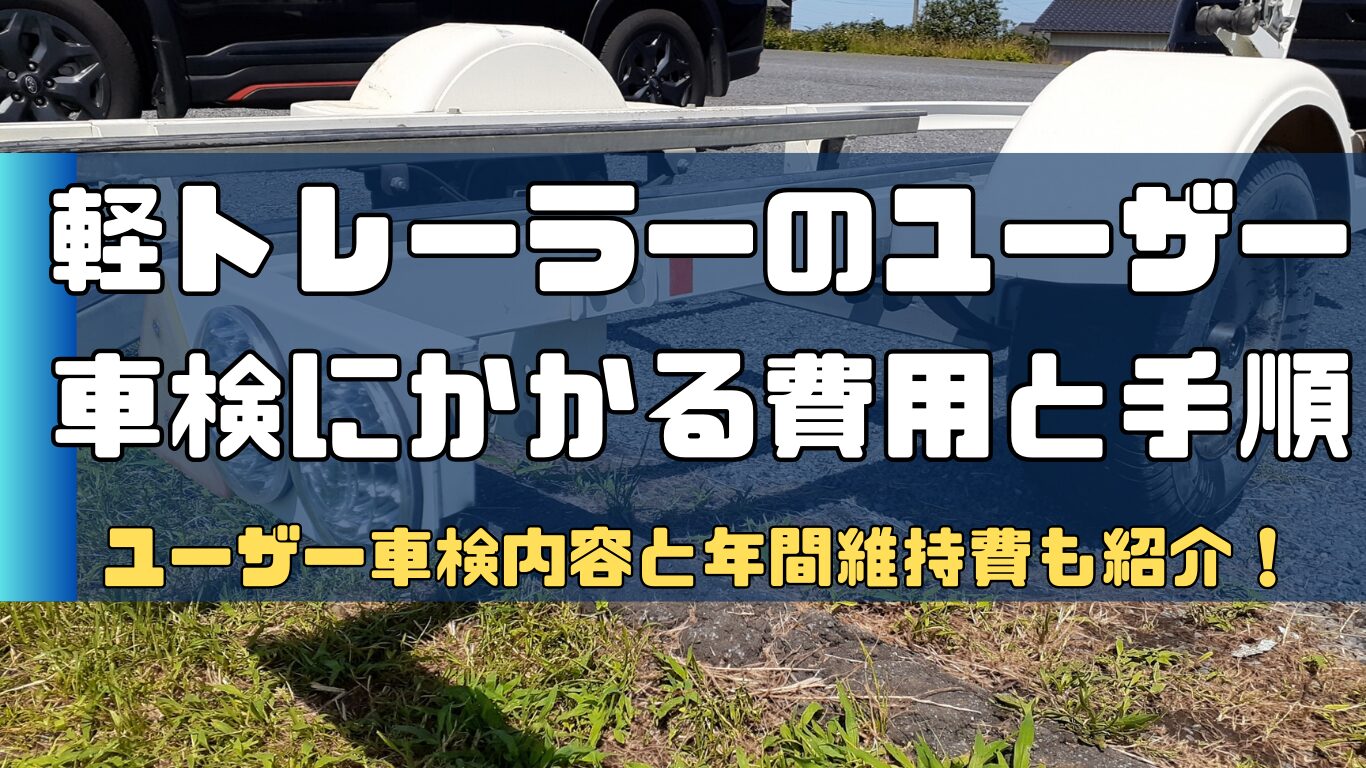



コメント