スーパーライトジギング(SLJ)は、軽量ジグを使い手軽に多彩な魚種を狙える近年人気急上昇の釣り方です。
マダイやイサキ、根魚から青物までターゲットは幅広く、初心者や女性でも楽しみやすいのが大きな魅力。とはいえ、ただジグを落として巻くだけでは釣果に差が出てしまいます。
そこで本記事では、マイボートや遊漁船でSLJを楽しんでいる経験をもとに、基礎となるタックルやセッティング、まず覚えるべき釣り方に加え、釣果を伸ばすための「11のコツ」を徹底解説します。
また、最初は釣れていたのに急に釣れなくなった時の理由や、対処方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
スーパーライトジギング(SLJ)とは?基礎と魅力を解説!

スーパーライトジギング(SLJ)は、手軽さと多彩なターゲット性で注目されているジギングスタイルです。
従来のジギングよりも軽量タックルと30〜80グラム程度の小型ジグを使うため、体力に自信のない人や初心者でも無理なく楽しめるのが大きな魅力です。
さらに、アジ、イサキ、カサゴ、マダイといった身近な魚から、青物や根魚まで幅広く狙える点も釣り人を引きつけます。浅場でイサキやカサゴを狙う日もあれば、潮流に応じてジグを替えて青物を狙うこともでき、状況に応じた戦略性が味わえます。
このようにSLJは、初心者のジギング入門としてもベテランの新たな挑戦としても適しており、少ない力で長時間楽しめ、釣果を得やすいスタイルです。
つまりSLJとは「誰でも気軽に、多彩な魚種と出会える近海ジギング」と言えるでしょう。
SLJタックルの基本セッティング

SLJで釣果を出すためには、「タックルの基本セッティング」が重要です。
なぜ基本セッティングが大切かというと、SLJが30〜80グラムの軽量ジグを中心としたジギングスタイルだからです。
軽量ジグをしっかり動かし、魚に魅力的に見せるには、柔軟性と感度を兼ね備えたロッドが必要で、細かい操作ができる相性のよいリールとの組み合わせが欠かせません。
また、使用するラインはジグの動きを阻害しないよう、PEライン0.6〜1号にリーダー12〜20ポンドを合わせるのが基本です。細めのラインを使うことでジグの動きが自然になり、魚が口を使いやすくなります。
このようにタックルバランスを整えることで操作性と感度が高まり、安定したSLJゲームが楽しめます。まずは基本セッティングを意識して準備しましょう。
SLJに最適なロッドやリール、ラインシステムについては下記の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
【完全ガイド】スーパーライトジギングとは?釣り方・おすすめタックル・狙える魚まで徹底解説!
釣り方の基本:底取り→糸ふけ回収→ワンピッチ→フォール

SLJで安定した釣果を得るには、まず基本操作を身につけることが大切です。
ジグの位置を正確に把握するため、最初は必ず底取りを徹底します。その後、ジグに力がしっかり伝わるよう素早く糸ふけを回収し、ワンピッチジャークでメリハリのあるアクションを加えます。
さらに、フォールを意識的に取り入れると、ジグがひらひらと落ちる動きが食わせの間を生み、低活性時やマダイ、根魚に効果的です。
このように、SLJで釣果を伸ばすには基本動作を繰り返し、バイトにつながるパターンを見つけることが重要です。まずは「底取り→糸ふけ回収→ワンピッチ→フォール」を正確に行ってみましょう。
釣果アップの11のコツ
| コツ | ポイント |
|---|---|
| 底取りの精度を上げる | 着底を正確に把握してレンジを外さない |
| レンジを幅広く探る | 底から中層まで刻んで魚の居場所を探す |
| ただ巻きの速度を刻々と変える | 魚種や活性に合わせてスロー/速巻きを使い分け |
| ワンピッチのピッチとストロークを変える | ピッチやストロークを変えて魚に慣れさせない |
| フォールで食わせる“間”を作る | フォールを入れてヒラヒラ落ちる動きでバイトを誘う |
| 風・潮に応じて誘い方を変える | 潮流や風の状況に合わせて巻き・フォールを調整 |
| ジグの重さ・素材を潮で替える | 潮速や水深に応じて鉛/TGを使い分ける |
| シルエットとカラーをベイトに合わせる | ベイトに似せることで違和感なく口を使わせる |
| ライン&ドラグ設定 | 号数を調整してジグの動きを最適化(詳細は別見出し) |
| アシストフックの向き・長さを魚種で変える | 魚種に応じてフック長さ・形状を調整してバラシを減らす |
| 魚種別攻略 | イサキ・青物は速巻き、マダイは中層、根魚は底中心で狙う |
ここでは、マイボートや遊漁船で得たSLJで釣果アップが期待できる11のコツについて解説していきますので、釣果で悩んでいる方は試してみてください。
1. 底取りの精度を上げる
SLJで釣果が出にくいときは、まず「底取り」をしっかり意識して行いましょう。
底取りができていると、船長の指示するタナに合わせやすく、ジグの位置を正確に把握できます。さらに、底付近にいるターゲットにもしっかりアピールできるため、結果として釣果につながる可能性が高まります。
そのため、基本に立ち返り、底取りを確実に行うことを常に意識することが大切です。
2. レンジを幅広く探る
SLJでは「レンジを幅広く探る」ことも有効です。
その理由は、同じポイントでも潮の速さやベイトの動きによってヒットゾーンが変化するためです。
SLJの基本は船長の指示したタナを狙い、ジグにアクションを加えてターゲットを誘うことですが、このとき指示タナだけでなく、前後のレンジも意識して探ることで釣果につながりやすくなります。
3. ただ巻きの速度を刻々と変える
SLJではただ巻き対応のジグも多くありますが、シンプルなただ巻きでも速度を変えることで釣果は大きく変わります。
その理由は、魚種や活性によって最適なスピードが異なるためです。速巻きは青物のリアクションを誘いやすく、スロー巻きはマダイやイサキに口を使わせやすい傾向があります。
釣果に差をつけたいなら、速度変化を意識しながらターゲットに合わせた巻き取りを心がけましょう。
4. ワンピッチのピッチとストロークを変える
SLJで魚を誘うには、ワンピッチジャークの幅とテンポを変えることが効果的です。
理由は、同じリズムだと魚が慣れて反応が薄れるためです。例えば短いピッチで細かく誘えばイサキや小型青物、逆に大きなストロークで力強く動かせばブリやヒラマサといった大型青物にアピールできます。
そのため、ピッチやストロークを自在に変化させることが幅広い魚種攻略につながり、釣果アップに直結します。
5. フォールで食わせる“間”を作る
SLJで狙う多くの魚は、ジグが落ちる瞬間にバイトします。そのため、フォールを意識的に取り入れて「食わせの間」を作ることが大切です。
落下中のジグは弱ったベイトのように見え、捕食本能を強く刺激します。実際、ただ巻きから一瞬止めてフォールを入れるだけで、マダイや根魚のヒット率は大きく上がります。
釣果を伸ばしたいなら、フォールを積極的に組み込むことを意識しましょう。
6. 風・潮に応じて誘い方を変える
SLJでは、風や潮の状況に応じて誘い方を調整することが釣果を伸ばす秘訣です。
SLJで使用するジグは30〜80グラムと軽量なため、風や潮が強いと動きやライン角度が変化し、普段通りのアクションが効かなくなることもあります。
そのため、潮が速いときは巻きを主体にテンポを上げ、潮が緩いときはフォールを多めに入れるなど、状況に応じた切り替えを意識することが重要です。
7. ジグの重さ・素材(鉛/TG)を潮で替える
SLJでは、潮の速さや水深に応じてジグを使い分けることが重要です。
理由は、重さや比重によって沈下速度やアクションが変化し、魚へのアピール力が大きく左右されるためです。
例えば、潮が緩いときは鉛ジグの自然な動きが効果的で、潮が速いときや深場ではタングステンジグの素早いフォールが有効です。このように状況に合ったジグを選ぶことで、釣果の安定につながります。
8. シルエットとカラーをベイトに合わせる
SLJで釣果を伸ばすには、マッチ・ザ・ベイトと呼ばれるベイトに合わせたジグ選びが不可欠です。
理由は、魚はその場で捕食している小魚に強く反応するためで、形や色が似ているほど口を使いやすくなります。小型ベイトが多いときはスリムシルエット、イワシが群れているときはブルーやシルバー系が効果的です。
このようにシルエットとカラーを意識することで、魚に違和感なくアプローチでき、より効果的にヒットにつなげられます。
9. ライン&ドラグ設定:PE0.6〜1号+リーダー12〜20lb
SLJで幅広い魚を攻略するには、ラインシステムの号数を適切に選ぶことが重要です。
理由は、ラインの太さによってジグの動きや到達レンジが大きく変わるためです。例えば、PE0.6号を使えば軽量ジグでも自然に落とせ、食い渋った魚にも口を使わせやすくなります。一方、青物を狙う場合はPE1号まで上げることで、ファイト中も安心です。
つまり、ターゲットや状況に応じたライン選択は、ジグの動きを魅力的に見せつつ、効率的に魚を誘うためのコツの一つです。
SLJに最適なラインについては、下記の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
【2025年最新】SLJにおすすめのPEライン11選!SLJ向きPEラインの5つの選び方
10. アシストフックの向き・長さを魚種で変える
SLJで確実にフッキングするには、アシストフックの向きや長さを魚種に応じて調整することが重要です。
例えば、イサキやカサゴなど口が小さい魚には短めでフックポイントが外向きのもの、青物やマダイなど大型魚には長めでしっかり刺さるタイプを選ぶと効果的です。
結論として、ターゲットに合わせたアシストフックの調整を行うことで、バラシやフッキングミスを減らし、釣果を安定させることができます。
11. 魚種別攻略:イサキ・青物は速巻き、マダイは中層、根魚は底中心
SLJで効率よく釣果を上げるには、魚の捕食層や活性に応じて、最適なレンジや巻きスピード、アクションを調整することが重要です。
例えば、イサキや青物は活性が高いため、速巻きでリアクションを誘うのが効果的です。マダイは中層でフォールやスロー巻きに反応しやすく、根魚は底付近を丁寧に攻めるのが基本です。
結論として、ターゲットごとにレンジや巻き方を調整することで、ジグのアピール力を高め、効率的かつ安定した釣果を得られます。
急に釣れなくなった原因と対象方法

SLJで最初は釣れていたのに、「回数を重ねるごとに釣果が悪くなる」「急に釣れなくなった」と感じる場合、経験上考えられる原因は主に次の2つです。
- SLJに慣れて上達した
- 大型魚に力負けしたことがある
SLJに慣れて上達した
SLJに慣れて上達すると、なぜ釣果が不調になるのか不思議に思うかもしれません。実は、操作に慣れることでジグの動きが正確になりすぎ、魚にとって魅力的に見えなくなる場合があります。
初心者の場合、ロッドのしゃくり方やリーリングがぎこちなく、ジグが弱ったベイトのように自然に動くことが多く、フォールも無意識に演出できています。これがいわゆる「ビギナーズラック」の理由です。
一方、中級者になるとジグはきびきび動くようになりますが、ターゲットの捕食衝動を引き出すほどの魅力はまだ十分ではありません。そのため、急に釣れなくなった場合は「フォール」の間を意識してみることが有効です。
SLJだけでなくジギング全般のジグは、ジャーキング中の動きだけでなく、フォール中のフラッシング効果も意識して設計されています。初心に戻り、ジグの動きとフォールの間を丁寧に意識することで、釣果が安定しやすくなります。
大型魚に力負けしたことがある
SLJでは不意に大型魚がかかることがありますが、使用するタックルでは力負けしてしまい、「ロッドを起こせない」「ラインを全て引き出される」など、SLJタックルでは対応できない状況に陥ることがあります。
この経験から、大型魚に対応しようとタックルを変更すると、逆に釣果が落ちる原因になります。
なぜなら、SLJは30〜80gの軽量ジグを扱う釣法であり、操作性や感度に優れたタックルバランスが不可欠だからです。ラインを太くしロッドパワーを上げると、軽量ジグの自然な動きが阻害され、魚に口を使わせにくくなります。
大型魚への対応はライトジギングや通常のジギングにステップアップするのが適切です。まずは、SLJタックルで扱えるサイズに合わせてセッティングを戻すことが、釣果を安定させるコツです。
SLJの次のステップであるライトジギングについては、下記の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
【完全ガイド】ライトジギングとは?基本タックルと釣り方のコツを紹介!
まとめ
スーパーライトジギング(SLJ)は、軽量タックルで手軽に多彩な魚を狙える近海ジギングの人気スタイルです。
釣果を安定させるには、底取りの精度やレンジ攻略、ただ巻きやワンピッチ、フォールなど基本の釣り方をマスターすることが第一歩です。さらに、ジグの重さや素材、シルエット・カラー、アシストフックの調整、魚種ごとの攻略法を組み合わせることで釣果を大きく伸ばせます。
本記事で紹介した11のコツを意識すれば、状況やターゲットに応じた効率的な誘い方が可能になるので、ぜひ参考にしてください。
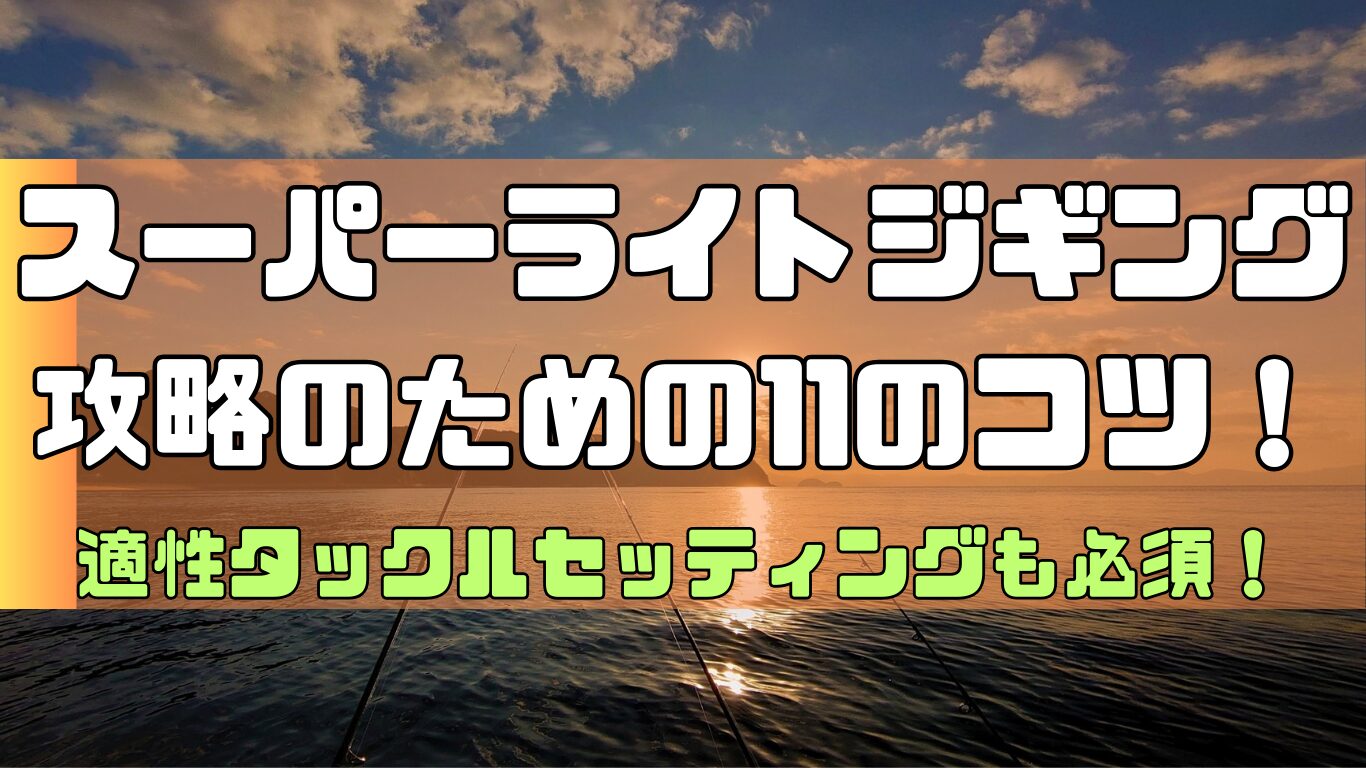

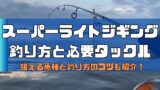

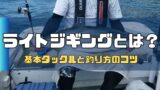


コメント